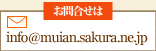当会は、主宰者の二度の大病(白血病、脳出血)からの生還の体験から「本当に大切な事は今この時を幸せに生ききること」という考えのもと、執着ではなく養生しながら大切に毎日を生きる為の知慧を様々な角度から提案していく会として約20年間活動を続けています。そしてたどりついた事は生と死はあわせ鏡、死を未来にあるものとせず、この時訪れるものとして今を養生することを発信しています。


(施術)
- 推拿(すいな)自然療法自然療法
無為庵での施術の他、自宅や指定会場での出張致します。 - ホメオストレッチ
- PNF療法
- キネシオテーピング療法
- 経絡気功療法
(イベント、ワーク)
- 呼吸気功法講座
- 家庭で役立つ中医学講座
- 写経座禅精進料理講座
- 無為庵春の森林浴と石窯ピザワーク
- 養生術講座(呼吸法と気功法)の指導
- 中医学(基礎学、中薬学、易学)の指導
- 食養生、時間養生の指導
- 精進料理教室・薬膳料理
- 自然体験ワーク
- 陰陽五行易学講座 その他
- 無為庵夏の沢登りと暗闇ワーク
- 無為庵秋の星空鑑賞会
- 無為庵冬の雪遊びワーク
- 伊勢神宮125社巡り
- 熊野古道を歩く
活動拠点

- みなかみ無為庵 群馬県利根郡みなかみ町永井637-4
- 前橋無為庵 群馬県前橋市天川大島町2-32-5
- 吹田無為庵 大阪府吹田市昭和町5-7
研究会代表
田村 泰久
090-4421-0690



文月7月に寄せて
先日、久々に新潟の一宮、弥彦神社と弥彦山の奥宮に参拝させていただき、冬は閉鎖でいけなかった西生寺の即身仏、弘智上人にお会いして来た。
江戸時代に約2500日の滝行と木食、つまり木ノ実だけ食べて腐りづらい体を求め、その後、土の中で断食しながら、ひたすら民衆の無病息災を祈って即身仏になられた上人様はその前で合掌させていただくと今でも生きている様に暖かい気を発している。
その御堂の前には上人様の言葉が書いてある。
「私は死ぬのではない。即身仏となって病いや飢え、苦しみ、悲しみに喘ぐ人々を救うために入定したのだ。願う者は私の前で祈りなさい。必ず私が救おう。」
解釈するとそのようにある。
私はこの上人様にお会いするとこの世が三次元、あの世が四次元で意識できる修行をされた上人様は祈る三次元の者達に四次元から手を差し伸べてくれる。そうすると三次元の者達は自らの道を切り開く覚悟と意識が持てる、そんなふうに思えるのだ。
上人様の御堂の近くにいつもは入り口が閉じている御堂がこの日は何故か開帳して、合掌するとそこにある言葉が書いてあった。
「生きることは矛盾と相剋を呑み込むこと」
衝撃だった。まさに今、私が求めていた言葉だ。
人が生きていく中で皆、殺生する。そして他人から見れば批判されるべきことを間違っているといわれる事もやって生きることもある。
そんな矛盾を呑み込み、相剋、つまりさまざまな障害や抵抗にあっても道を信じて進むそれが呑み込むことだと思う。そこには自分を信じるからストレスからは解放されて幸せ感が溢れてくる相生の生き方が構築できる、そう思えるのだ。人生120年の折り返しを過ぎてこの言葉にようやく出会えた。私はそのために病気をいただき、別れを経験して怪我もしてそれでも多くの生徒さんたちや大切な人にも出会えて今が一番幸せな時を過ごせていると思う。
漫画で7月5日大地震説、コロナワクチン無効説、備蓄米放出問題
いったいこの国はどう誘導されて行くのか?私にはわからないが自分を信じて矛盾も相剋も呑み込み相生に生きたいものだ。




「速効!!10秒で効く5ツボ」
2025年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 補講 |
3 |
4 |
5 中医学講座 |
6 養生術実践勉強会 |
|
7 出張施術
|
8 養生術実践勉強会 |
9 |
10 施術会 |
11 家庭やサロンで役立つ中医学講座 |
12 施術会 |
13 |
14 施術会 |
15 写経会 |
16 出張施術 |
17
|
18
|
19 |
20 |
21 出張施術
|
22
|
23
|
24 出張施術 施術会 |
25 呼吸気功講座 施術会 |
26 施術会 家庭やサロンで役立つ中医学講座
|
27 早朝座禅会 |
28 施術会
|
29 養生術実践勉強会
|
30
|
31
|
|
|
※日程は変更または中止になる場合がありますので直接確認して下さい
2025年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 出張施術 |
3 養生術実践勉強会 |
||||
4
|
5 養生術実践勉強会 |
6
|
7 施術会 |
8 家庭やサロンで役立つ中医学講座 |
9 施術会 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16 みなかみ無為庵 |
17 みなかみ無為庵 |
18
|
19 みなかみ無為庵
|
20 |
21 出張施術 |
22 呼吸気功講座
|
23 施術会 |
24 早朝座禅会 |
25
|
26 養生術実践勉強会 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31 |
※日程は変更または中止になる場合がありますので直接確認して下さい